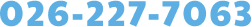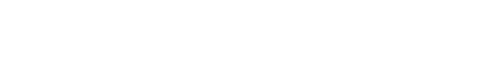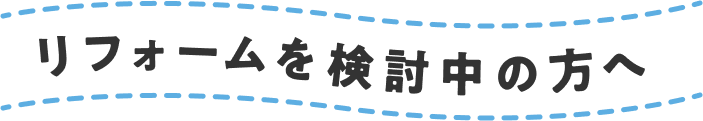マンションの床に1年で隙間ができた?原因と対処法を徹底解説
引っ越してからまだ1年ほどしか経っていないのに、床の継ぎ目にうっすら隙間が見える。
「これって施工ミス?」「放っておいて大丈夫なの?」
そんな不安を感じていませんか?
実は、マンションの床にできる隙間の多くは“張った時の寸足らず”か“自然現象”かです。(シートフローリングは寸足らずの可能性が高い)
木材は生きています。
湿度や気温の変化に反応して、呼吸するように伸び縮みします。
特に新築やリフォーム後1年以内は、床材が環境に慣れていく“落ち着きの期間”なのです。
この記事では、マンションの床に1年で隙間ができる原因、様子を見るべきケースと注意が必要なケースの違い、
そして、DIYでの応急処置や業者に依頼する際の費用相場まで、わかりやすく解説します。
マンションの床に1年で隙間ができるのは自然なこと
まず知っておきたいのは、「床の隙間は不良」ではないということです。
とくに木質系フローリング(無垢材・突板など)では、1年を通して季節ごとに伸縮が起こります。
木材は呼吸する素材
木材は、湿度の高い夏には水分を吸って膨張し、乾燥する冬には水分を放出して収縮します。
この動きは自然現象であり、どんなに高品質な床材でも完全には防げません。
たとえば冬場に1mm程度の隙間ができても、梅雨時期や夏になると自然に閉じていくケースがほとんどです。
1年というサイクルを通してみると、木材は「呼吸」をしているのです。
新築・リフォーム直後は「落ち着き期間」
施工して間もないフローリングは、まだ周囲の環境に馴染んでいません。
施工時に乾燥した状態だった木材が、居住環境(湿気・温度)に適応するまでに微細な変化が起こります。
その結果、張り終えてから1年以内に隙間が生じるのはむしろ自然なのです。
この期間を「ならし期間」と考え、すぐに手を加えず1年程度は様子を見るのが基本です。
隙間の大きさで判断するポイント
床の隙間は、発生した位置や広がり方で判断が変わります。
下の表は、一般的な目安です。
| 隙間の状態 | 考えられる原因 | 対応方法 |
|---|---|---|
| 約1mm以内で季節により変化 | 木材の伸縮(自然現象) | そのまま様子を見る |
| 2mm以上で広範囲に発生 | 下地の沈み・施工不良 | 業者に相談 |
| 一部だけ段差や沈みを感じる | 下地の緩み・構造歪み | 専門点検を依頼 |
| 冬でも閉じない隙間がある | 接着不良・乾燥過多 | 補修検討または張り替え |
隙間の幅が「名刺一枚程度(1mm前後)」であれば、多くの場合は自然に戻ります。
しかし、隙間が広がり続ける・足元が沈む・音が鳴るといった症状がある場合は、早めの点検が必要です。
1年様子を見るのが基本な理由
乾燥する冬にできた隙間は、湿気の多い季節になると戻る傾向があります。
特に無垢材のフローリングでは、この“呼吸”が顕著です。
季節による変化は自然のリズム
湿度が30%以下の冬季には木が縮み、50〜70%の梅雨時期には膨張します。
このため、冬にできた隙間は梅雨には閉じるケースが多く、補修を急ぐと逆に“膨張で盛り上がる”リスクもあります。
このような理由から、最低でも四季を一巡する1年は様子を見ることが推奨されます。
室内環境の整え方もポイント
木材の動きを穏やかにするためには、加湿器や除湿器を活用して室内の湿度を一定に保つことが大切です。
また、床暖房がある家庭では、急激な加熱や乾燥を避け、徐々に温度を上げる工夫も有効です。
DIYでできる応急処置
小さな隙間であれば、簡単なDIYで一時的に見た目を整えることができます。
ただし、根本原因を解決するものではないため、やりすぎには注意が必要です。
パテやコーキング剤で埋める
市販のフローリング用補修パテやコーキング剤を使えば、隙間を目立たなくできます。
床の色に合わせた補修材を選び、ヘラで薄く均すように塗り込みます。
乾燥後に余分な部分を拭き取ることで、自然な仕上がりになります。
ただし、木材が再び膨張するとひび割れや盛り上がりが発生することがあるため、季節を見極めて施工しましょう。
木くずパテを活用する
木材の粉とボンドを混ぜた“木くずパテ”は、天然素材に近い質感で補修したい場合におすすめです。
無垢材フローリングに使用すると、経年変化とともに馴染みやすくなります。
ワックスで隙間を目立たなくする
隙間がごくわずかな場合、床全体にワックスをかけることで光の反射が均一になり、目立ちにくくなります。
保護効果も高まり、汚れや乾燥を防ぐことができます。
業者に相談した方が良いケース
1年経っても隙間が戻らない、または広範囲に渡る場合は、施工不良や構造的な問題の可能性があります。
以下のような症状がある場合は、早めに専門業者へ相談しましょう。
- 隙間が2mm以上あり、全体に広がっている
- 床材が浮いたり沈んだりする感触がある
- 床鳴りや沈み込みが同時に発生している
- 床暖房のある部屋で部分的に隙間が残る
特に床暖房を設置しているマンションでは、熱の影響で接着剤が劣化しやすく、専門知識が必要になります。
賃貸マンションの場合の注意点
賃貸物件では、自己判断で補修を行うと退去時に「原状回復義務」のトラブルになる可能性があります。
まずは管理会社やオーナーに連絡し、指示を仰ぎましょう。
管理側で修繕費を負担してくれるケースもありますが、
自分で市販パテなどを使用して補修した場合、後の修理が難しくなることもあるため要注意です。
専門業者による修繕内容と費用相場
隙間の原因が施工不良や下地の変形だった場合は、専門業者による修繕が必要です。
施工方法や費用の目安は以下の通りです。
| 修繕方法 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 隙間充填補修 | パテや木材パウダーで埋める簡易補修 | 約1万円〜3万円 |
| 接着補強工法 | フローリング下に専用接着剤を注入 | 約3万円〜5万円 |
| 下地補修 | 床下の緩み・歪みを修正 | 約5万円〜10万円 |
| 張り替え工事 | 床材の全面交換 | 10万円〜30万円以上 |
下地や構造に問題がある場合は、見た目を整えるだけでは再発します。
そのため、「隙間が閉じない+床が動く」ような状態なら、根本的な補修を検討することが重要です。
隙間を防ぐためにできる日常のお手入れ
木材の動きを完全に止めることはできませんが、
普段の暮らしの中で隙間を最小限に抑える工夫は可能です。
- 室内の湿度を40〜60%に保つ(加湿・除湿で調整)
- 床暖房の温度を急激に上げない
- 定期的にワックスをかけて保護膜を作る
- 直射日光を避けるためにカーテンやブラインドを使用する
こうした日常的なケアを心がけるだけで、木材の安定性が高まり、隙間の発生を抑えやすくなります。
まとめ:1年は様子を見て、それでも戻らなければ相談を
マンションの床に1年ほどでできる隙間は、多くの場合「自然現象」です。
木材は湿気と温度に敏感に反応し、季節によって伸び縮みします。
ただし、
- 隙間が広がる一方
- 段差や沈みがある
- 床鳴りが併発している
こうした症状が見られる場合は、施工上の問題の可能性があるため、専門業者の診断を受けましょう。
弊社では、マンション特有の下地構造・床暖房対応・防音仕様まで熟知した職人が現地調査を行い、最適な補修方法をご提案します。
住まいの快適さを保つためにも、「少しおかしいな」と感じた時点でご相談ください。
毎日歩く床だからこそ、違和感のない“心地よい足触り”を取り戻しましょう。